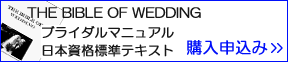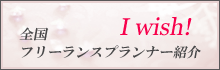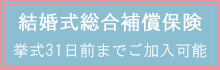ビジュアル雑誌の創刊
バブル崩壊後の1993年からゼクシィに代表される、写真が紙面の7割を占める多くのビジュアル雑誌が創刊された。ビジュアル雑誌の創刊前は、披露宴会場と言えば6割がホテル、3割が専門式場であったが、その詳細情報はクローズされていた。しかし、ビジュアル雑誌の創刊により、情報は一気にオープンとなり、ブライダルの全貌が一般の人たちにもビジュアル情報として伝えられるようになった。
終身雇用が日本の企業の根幹を担う時代は、1億2千万人総中産階級といわれ、貧富の差がほとんどなく、大金持ちも少なかったが、貧乏人も少なく平均的な人が全体の相当数を占めていたので平均的という言葉が美徳とされた。「出る杭は打たれる」ということばもこの時代を表す言葉なのだ。こうした日本の慣例もブライダル業界においては、ビジュアル雑誌の創刊と終身雇用の崩壊により平均的であることに対する美徳感覚に大きな変化が生じたのだ。ブライダルにおいてオリジナリティという言葉は、この頃に生まれた言葉である。
ゲストハウスの出現
つまり、人と同じである必要がない。もっと個人の個性を表現していいのだという感覚が広まった結果、それまでのホテルウエディングは、「お仕着せウエディング」と揶揄され、オリジナリティという言葉が新郎新婦のニーズとなっていった。このニーズが、プロデュース会社を生んだのである。
そして堰(せき)を切ったかのように1997年ゲストハウスの第一号店がオープンすると、このカテゴリーはわずか10年足らずでブライダル全体の20%以上を占めるようになった。このころのホテルは低迷期で、婚礼単価も大きく落としていた時期であったが、高単価なゲストハウスの好影響を受け、ホテルは単価の底上げができて、実質ホテルがゲストハウスに牽引されるという時期もあった。
この頃になると、婚姻件数も減少する一方デフレ経済の影響を大きく受け、経済が大きく冷え込むと同時に、給与も低迷し「無婚」層が増えだし、授かり婚の激増も無婚に拍車をかけた。2005年の調査では挙式披露宴を行っているのは全体の60%しかいないという状況が明らかになった。つまり、婚姻数の40%のカップルが無婚ということだ。
無婚対策をどう考えるか
日本の婚礼は、装置産業の域を出ないうちは、無婚対策は非常に難しいと考えられる。欧米における結婚は、シビルウエディングという宗教色を廃した挙式を役所で行うことで、法的に結婚が認められるというのが一般的であり、日本のような挙式に対する認識はむしろ珍しい。
実際、私の運営するIWPA国際ウエディングプランナー協会では、東京都のある区役所で挙式を行う1業者として認められているが、そこで挙式する新郎新婦が増えてきているが、衣裳もセミフォマールな服装で、人前式を行うという人も多く、費用的にも安価であるが、内容的に満足される方が多い。
装置産業でも婚礼特化型の施設におけるビジネス発想は、無婚層に対しては相反する発想であり、無婚を減少させる方向には決して動かない。顧客ニーズにおいて、様々な階層やジャンルが存在するのは当然のことであるが、企業の利益追求から少し視線を移して、文化や伝統、慣習の継承や伝承といったことをもう少し考えてもいい時期ではないかと思う。